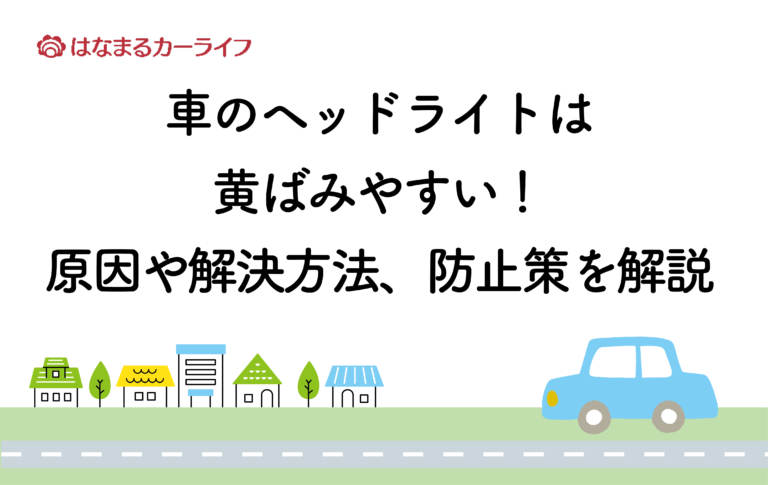車のライトは黄ばみやすい!原因から落とし方、便利グッズまで紹介
車のライトの黄ばみは、多くのドライバーが直面する悩みの種です。
些細な問題に思えるかもしれませんが、実は安全性や車の外観に大きな影響を与えます。
この記事では、ライトが黄ばむ原因や放置するリスク、そして対処法について解説します。
日々の運転をより安全に、そして愛車をより美しく保つために、ライトのメンテナンスの重要性を理解しましょう。
車のライトは黄ばみやすい!その原因は?
ひと昔前までは「鮮やかなカラーの塗装は色落ちしやすい……」などと言われてきました。
しかし最近では技術の発達により、キレイな状態を長く保てるようになっています。
その一方で車のライトの黄ばみだけは、長年にわたってオーナーを悩ませている問題です。
その原因としては次の4つがあげられます。
ライトの素材
車のヘッドライトが黄ばみやすい主な理由の一つに、ポリカーボネート樹脂素材の使用があります。
この素材は、耐衝撃性や耐熱性に優れ、軽量で加工しやすいという利点があるため、現代の車のヘッドライトに広く採用されています。
しかし、ポリカーボネート樹脂には紫外線に長期間さらされると化学変化を起こし、表面に茶褐色の「状態変化物質」が結晶のように発生してしまいます。
この変化が黄ばみの正体です。さらに、紫外線による劣化は樹脂の構造を不安定にし、活性酸素との結合を促進します。
これは例えると、樹脂の「錆」のようなものです。
通常、ヘッドライトの表面には紫外線や傷から保護するためのコーティングが施されていますが、時間の経過とともにこのコーティングが劣化し、剥がれてしまいます。
コーティングが剥がれた部分から紫外線や水分、酸素が直接ポリカーボネート樹脂に接触することで、黄ばみの進行が加速します。
洗車による傷
車のライトが黄ばみやすくなる理由の一つに、洗車による傷があります。
洗車時に使用するスポンジや布、あるいは自動洗車機のブラシなどが、ライトのプラスチック表面に微細な傷をつけてしまうことがあるためです。
これらの傷は、肉眼では見えないほど小さいものもありますが、時間とともに蓄積されていきます。
微細な傷は、ライトの表面を粗くし、光の散乱を引き起こします。
その結果、ライトの透明度が低下し、黄ばみやくもりの原因となるのです。
さらに、傷ついた表面は、汚れや埃、紫外線などの外部要因に対してより脆弱になります。
これにより、プラスチックの劣化が加速され、黄ばみがさらに進行します。
ライト内部の異物混入
車のライトが黄ばみやすくなる理由の一つに、ライト内部の異物混入があります。
車のライトの内部には小さな隙間が存在することがあり、そこから水や埃、虫などの異物が侵入する可能性があります。
車のライト内部に混入した異物は、ライト内部の環境を変化させライトの劣化を早める原因となるため注意が必要です。
特に水分の侵入は深刻な問題を引き起こします。
ヘッドライトの内部は、点灯時に高温になるため、侵入した水分が蒸発と結露を繰り返すことになります。
その結果、ヘッドライトのレンズ内側に水垢や曇りが発生し、徐々に黄ばみが進行していくのです。
これらの異物は、ヘッドライト内部の環境を変化させ、劣化を促進させる要因となります。
また、埃や虫などの有機物が混入した場合、高温多湿の環境下で分解され、化学反応を引き起こすこともあります。
外側から対策をしているのに、まったくキレイにならない……といったときは、内側に汚れが付着しているかもしれません。
熱によるダメージ
車のライトが黄ばみやすくなる理由の一つに、熱によるダメージがあります。
ヘッドライトのバルブは高温になるため、その熱がライトカバーに伝わります。
ヘッドライトの素材であるポリカーボネート樹脂の耐熱温度は約120度と比較的高いものの、長期間にわたる熱の影響は素材の劣化を引き起こします。
特に、渋滞時などエンジンルーム内の温度が上昇する状況では、熱によるダメージがより大きくなるため劣化が進んでしまうでしょう。
車のライトの黄ばみを放置するリスク
車のヘッドライトの黄ばみを放置すると、いくつかの重大なリスクが生じます。
視認性の低下
まず最も大きなリスクは、視認性の低下です。
ヘッドライトが黄ばむと、光の透過率が低下し、前方の視界が暗くなります。
特に夜間や悪天候時の運転において大変危険です。
視界が十分に確保できないと、急な飛び出しや障害物の発見が遅れ、事故のリスクが高まります。
さらに、ヘッドライトは他の車や歩行者に自車の存在を知らせる重要な役割も果たしています。
光量不足は周囲からの視認性も低下させ、事故の危険性を増大させます。
車検に通らなくなる
車のライトの黄ばみを放置すると車検が通らなくなる可能性が高まります。
ヘッドライトの光量や色味には規定があり、黄ばみによって基準を満たさなくなると、車検に合格できないためです。
これは予期せぬ出費や手間につながる可能性があります。
ヘッドライトの交換
ライトの黄ばみを放置すると、ヘッドライトの交換が必要になることもあります。
黄ばみが進行し過ぎると、表面のクリーニングや研磨では対処できなくなるためです。
その結果、ヘッドライトのカバー部分や本体の交換が必要になる場合があります。
特にLEDヘッドライトの場合、高額な出費を強いられる可能性があります。
ヘッドライトの黄ばみを落とす方法
ヘッドライトの黄ばみを落とすには、次の3つの方法が効果的です。
- 市販のヘッドライトクリーナーを使う
- 歯磨き粉を使う
- プロに依頼する
それぞれ詳しく見てみましょう。
市販のヘッドライトクリーナーを使う
ヘッドライトの黄ばみを落とし方の1つに市販のヘッドライトクリーナーを使うことが挙げられます。
クリーナーに含まれる研磨剤が、ヘッドライトの表面に付着した酸化物を削り落とすためです。
市販のヘッドライトクリーナーには、様々な研磨剤が配合されており、黄ばみの程度に合わせて選べます。
具体的な使用方法は次の通りです。
- 洗車をして水分をしっかりふき取り乾燥させる
- クリーナーを付属のスポンジやクロスに適量つけて、黄ばんだ部分を円を描くように磨く
- 水で洗い流し乾いたタオルで拭く
クリーナーでヘッドライトを磨くとき、力を入れて擦り過ぎるとヘッドライトのレンズ面を傷つけてしまう恐れあるため注意が必要です。
ヘッドライトクリーナーを使うことで、比較的簡単に黄ばみを落とすことができ、ヘッドライトの見た目を新品のように蘇らせることができます。
ただし、深い傷やひどい黄ばみの場合は、クリーナーだけでは効果が期待できないこともあります。
歯磨き粉を使う
ヘッドライトの黄ばみを落とし方の1つに歯磨き粉を使うことが挙げられます。
歯磨き粉の研磨剤は、歯の汚れを落とすために設計されているため、ヘッドライトの黄ばみを落とすのにも効果が期待できるためです。
しかし、歯磨き粉の種類によってはヘッドライトのレンズ面を傷つけてしまう可能性があります。
とくに研磨力が強い歯磨き粉は、ヘッドライトのコーティングを剥がしてしまう恐れがあるため注意が必要です。
さらに歯磨き粉の中には、ヘッドライトの素材であるポリカーボネートを浸食する成分が含まれていることもあります。
歯磨き粉を使用して黄ばみを落とす場合は以下の点にご注意ください。
- 研磨力が弱い歯磨き粉を選ぶ
- 柔らかい布を使用して磨く
- 力を入れて擦らない
歯磨き粉を使用する方法は、お金もかからずすぐにできる黄ばみ落とし法ですが、可能な限り市販のヘッドライトクリーナーを使用した方がよいでしょう。
プロに依頼する
ヘッドライトの黄ばみを落とし方の1つにプロに依頼する方法が挙げられます。
プロに依頼すれば、専用の機材と技術を使って、黄ばみを確実に除去してくれるためです。
深い傷やひどい黄ばみでも、綺麗に復元してくれます。
また自力で黄ばみ落としをするよりも手間なく短時間でヘッドライトが綺麗になるでしょう。
プロに依頼する場合は、カー用品店や自動車整備工場に依頼します。
ただし、プロに依頼すると施術費用として3,000円~15,000円かかります。
自力でするよりも費用がかかりますが、依頼すれば黄ばみ除去だけでなくコーティングを施して黄ばみ防止することも可能です。
プロに依頼することで、より確実かつ美しい仕上がりを得ることができます。自力でのヘッドライト磨きに自信がない方は、プロに相談してみるのも良いでしょう。
ヘッドライトの黄ばみを予防する方法
ヘッドライトの黄ばみを予防するには、次の3つの方法が効果的です。
- こまめな洗車
- コーティング
- ガレージ保管
ヘッドライトの黄ばみを防止するため、こまめな洗車を実施しましょう。
ヘッドライトに付着した汚れや虫の死骸は、時間が経つと紫外線と反応して黄ばみの原因となるためです。
こまめに洗車することで、これらの汚れを洗い流し、黄ばみの進行を遅らせることができます。
洗車後は、水滴をすぐにふき取り乾燥させるのを忘れないようにしましょう。
水滴がレンズに残っていると、水垢の原因になることがあるためです。
コーティング
ヘッドライトの黄ばみを防止するため、コーティングを実施しましょう。
コーティングをするとヘッドライトの表面に保護膜を形成し、紫外線や汚れからヘッドライトを守ってくれるからです。
また洗車後の水垢の付着も防ぎ、ヘッドライトをいつもクリアな状態に保つことができます。
コーティングの方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
ガレージ保管
ヘッドライトの黄ばみを防止するため、車はガレージに保管しましょう。
車を屋外に駐車するとヘッドライトの黄ばみの原因となる紫外線にさらされ、虫の死骸や雨風などの汚れも付着しやすくなるためです。
ガレージに車を保管することで、これら黄ばみの原因から車を守ることができ、黄ばみの進行を遅らせることができます。
ただ、自宅の立地によっては、ガレージの設置が難しいケースもあるでしょう。
ガレージの設置が難しい場合は、カーポートやカーカバーを利用するのも一つの方法です。
これらのアイテムも、紫外線から車を保護する効果が期待できます。
まとめ:車のライトはこまめに掃除して黄ばみを防止しよう
車のライトに使われている素材は、耐衝撃性や耐熱性に優れていますが、紫外線に弱いというデメリットがあります。
また車の正面にあるため走行中に小さな小石などで傷つきやすい部分です。
そのため、こまめに黄ばみを取るメンテナンスをしないと、ライトの黄ばみが進行し、ライトの光量が少なくなってしまいます。
そうなると、事故リスクが高まるため大変危険です。また、車検にも通らなくなる可能性もあるでしょう。
車のライトの黄ばみはセルフメンテナンスでも対応できますが、黄ばみが進行してしまうと、素人では黄ばみを落とせません。
プロに依頼して車のライトの黄ばみを除去してもらいましょう。
福岡県中間市で、車のライトの黄ばみにお悩みの方は中間ダイハツにご相談ください。
中間ダイハツでは、ライトの黄ばみをチェックし、黄ばみ除去はもちろんのこと、黄ばみが進行したライトの交換にも対応しています。
ライトの黄ばみのセルフメンテナンスの方法についても、アドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。